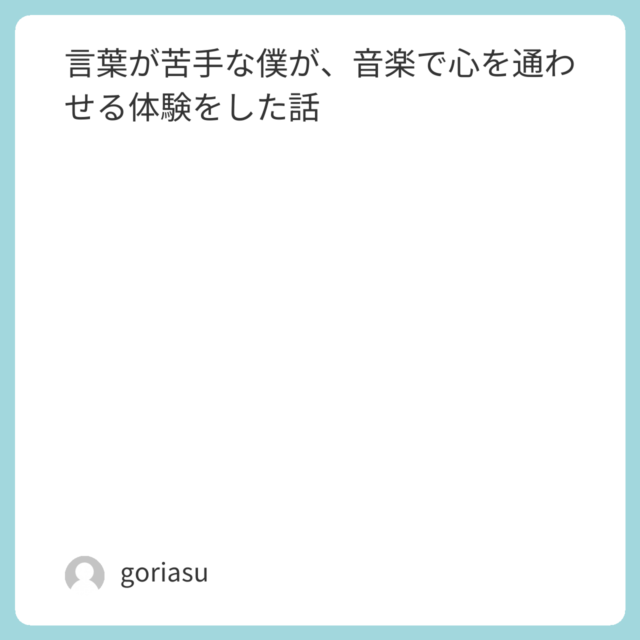 メルマガバックナンバー
メルマガバックナンバー 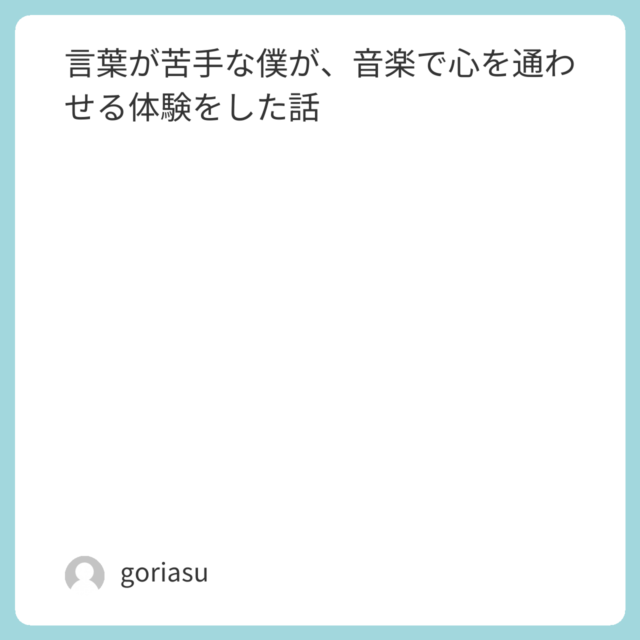 メルマガバックナンバー
メルマガバックナンバー 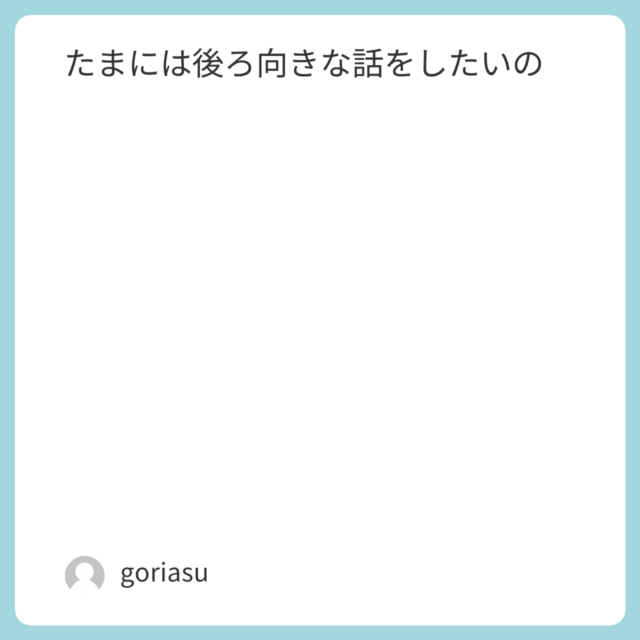 メルマガバックナンバー
メルマガバックナンバー たまには後ろ向きな話をしたいの
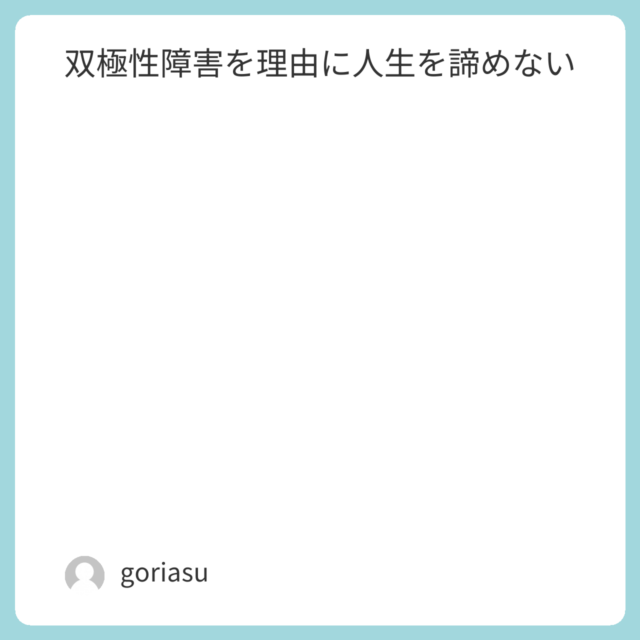 メルマガバックナンバー
メルマガバックナンバー 双極性障害を理由に人生を諦めない
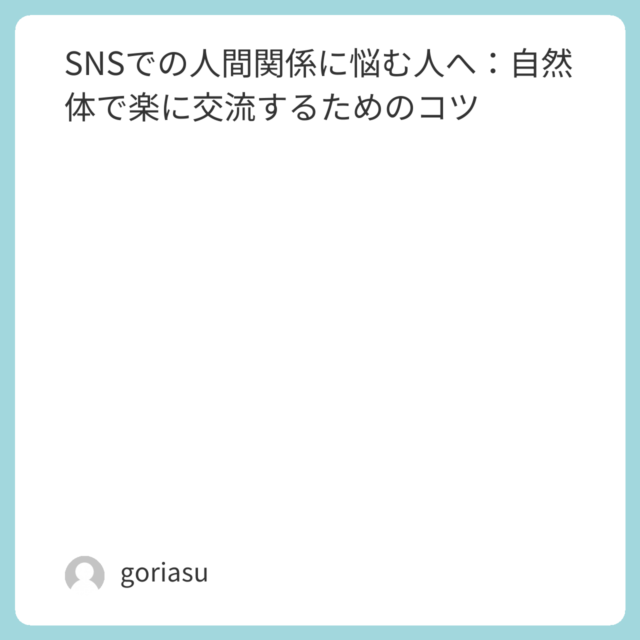 マインド
マインド SNSでの人間関係に悩む人へ:自然体で楽に交流するためのコツ
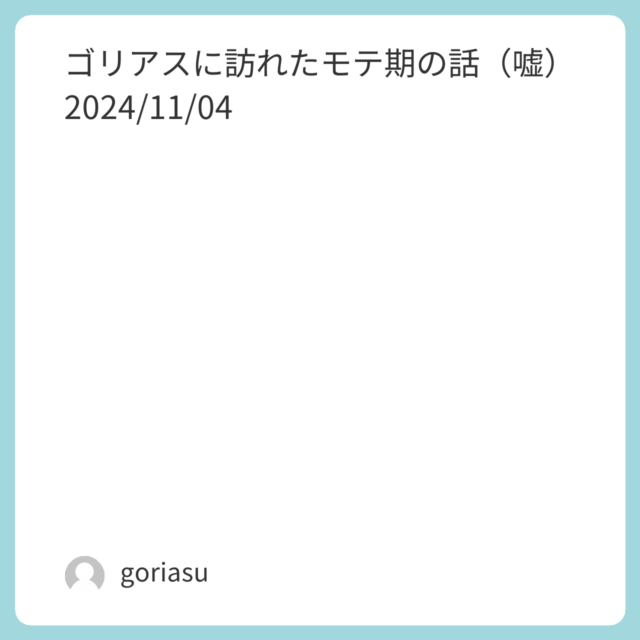 メルマガバックナンバー
メルマガバックナンバー ゴリアスに訪れたモテ期の話(嘘)2024/11/04
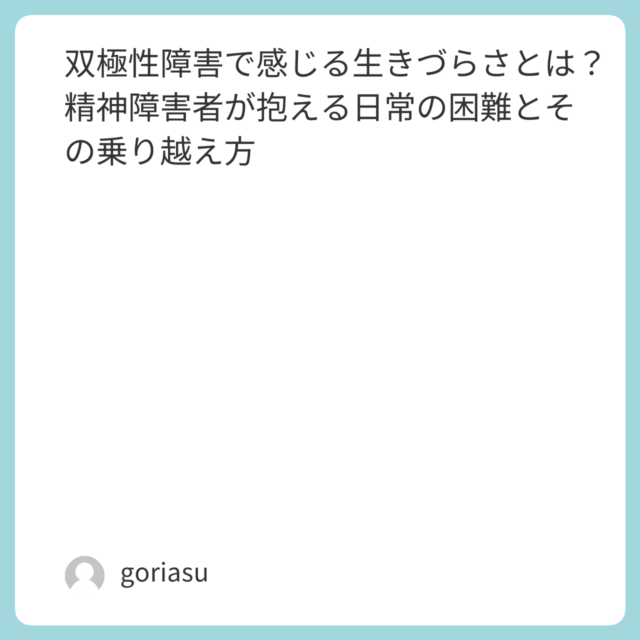 マインド
マインド 双極性障害で感じる生きづらさとは?精神障害者が抱える日常の困難とその乗り越え方
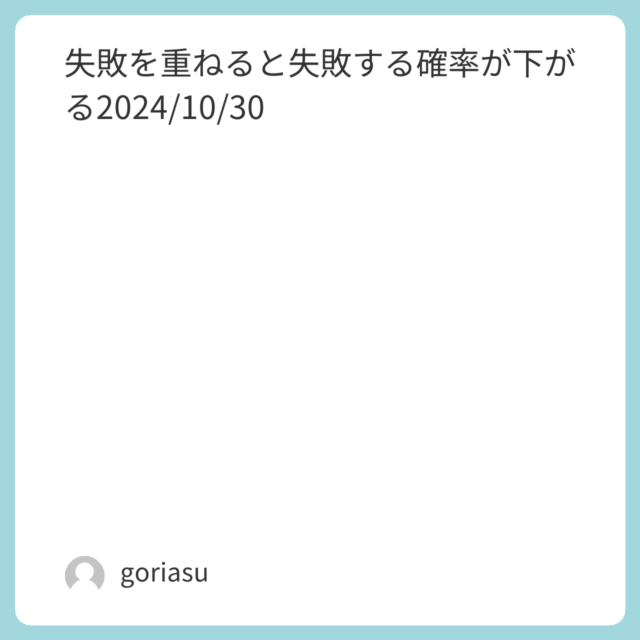 メルマガバックナンバー
メルマガバックナンバー 失敗を重ねると失敗する確率が下がる2024/10/30
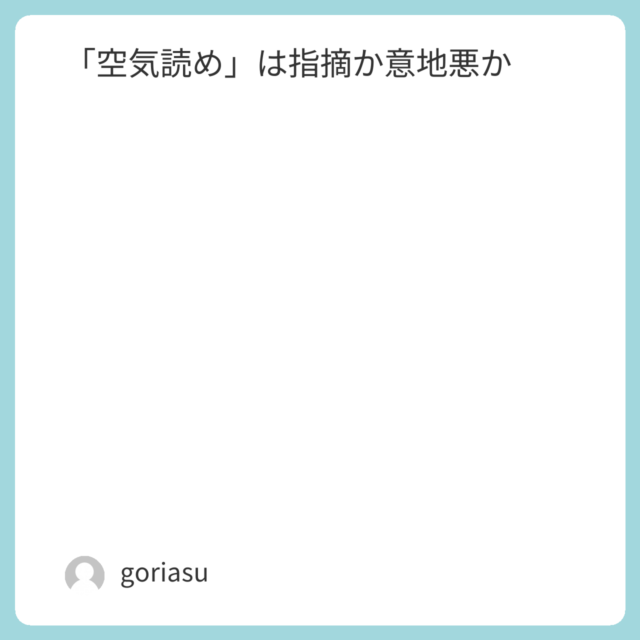 マインド
マインド 「空気読め」は指摘か意地悪か
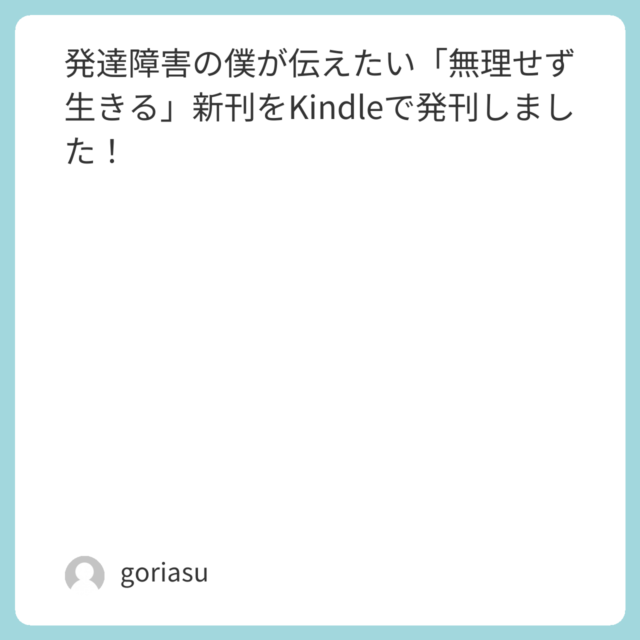 マインド
マインド 発達障害の僕が伝えたい「無理せず生きる」新刊をKindleで発刊しました!
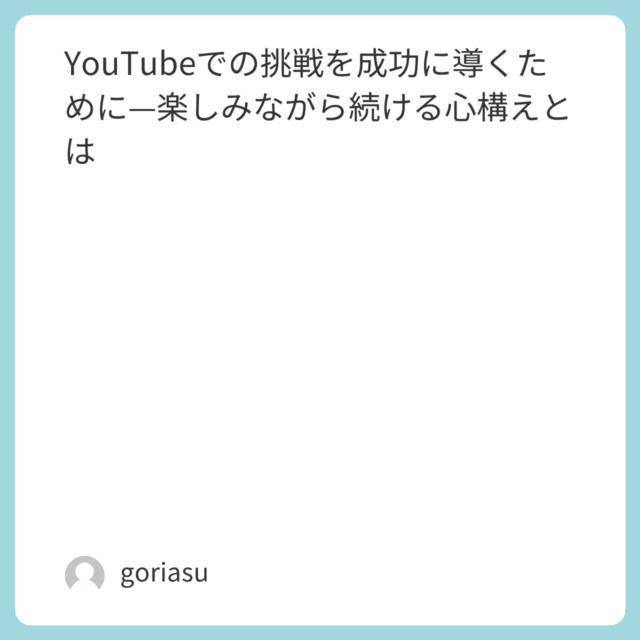 お金
お金